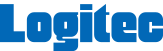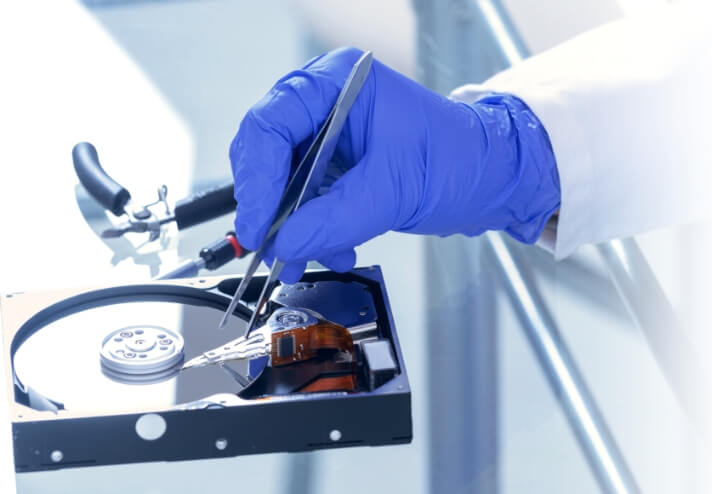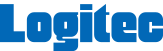パソコンやスマートフォンなどを日々使っている際に怖いのが、保存したデータが突然消えてしまうことです。しかし、万が一データがデバイスから消えてしまったとしても、バックアップを取っておけばデータの完全な消失は回避できる可能性があります。
では、データのバックアップは具体的にどのように行えば良いのでしょうか。
この記事では、パソコンやスマホでデータのバックアップを取る重要性や、データバックアップの具体的な手順をご紹介します。
1 データのバックアップはなぜ必要?

パソコンやスマートフォンなどに保存するデータの量は、基本的にはデバイスを使う期間が長くなるほど増えていきます。しかし、機械である限り故障や不具合が突然起きる可能性は捨てきれません。
端末を落としたり、データを間違って削除したりといった、人為的なミスでデータが消えてしまうケースも考えられます。
デバイスそのものは買い替えや修理によって使い続けられますが、消えてしまったデータの復旧は簡単ではありません。仕事で使うデータの場合は、信用問題にもつながります。
「データは消える恐れがあるもの」と認識し、消えると困るデータは全てバックアップを取っておくことが重要です。
また、データの復元が容易になったり、デバイスの環境移行をスムーズに行える点も、バックアップを取っておくメリットといえます。
2 データバックアップの種類

バックアップの対象範囲は、OSや設定など、システムの構成要素を全て含めた「システムバックアップ」と、データのみコピーする「データバックアップ」に分けられます。
データバックアップは、その方法からさらに3つに大きく分けることが可能です。データのバックアップを取る際は、用途に適した方法を選択しましょう。
データバックアップの種類とそれぞれの特長は、以下のとおりです。
2-1 フルバックアップ
バックアップ対象となる全てのデータを、丸ごとバックアップする方法です。基本的に、初めてバックアップをする際はフルバックアップを取ることになります。
データ容量によってはバックアップに時間がかかり、保存先のストレージ容量を多く消費する点がデメリットです。別の方法と組み合わせて使うと、効率的にバックアップを行えます。
2-2 差分バックアップ
前回のフルバックアップから、変更があったデータだけコピーする方法が差分バックアップです。フルバックアップよりもストレージ容量や作業時間を抑えられます。
ただし、全ての変更点を都度バックアップするため、徐々にストレージを圧迫する可能性があります。
2-3 増分バックアップ
前回のバックアップから変更されたデータだけをコピーする方法です。バックアップにかかる時間が短いうえに、保存に必要な容量も少なくできます。
特定の時点でバックアップデータが破損していた場合、それ以降のデータ復元が難しくなる可能性がある点がデメリットです。
3 バックアップに使えるストレージは?

同じデバイス内にデータのコピーを増やしても、デバイスが故障したらそのデータを読み取ることはできません。データのバックアップを行う場合、バックアップデータはスマートフォンやパソコンの内蔵ストレージ以外の場所に保存しましょう。
データのバックアップ先の一例としては、以下のメディアが挙げられます。
• 外付けHDD
• ネットワークHDD(NAS)
• 外付けSSD
• クラウドストレージ(オンラインストレージ)
• 光学ディスク(DVD、ブルーレイディスクなど)
• USBメモリ など
HDDは大容量な一方で物理的な衝撃に弱い、クラウドストレージはインターネット環境がないと使えないなど、それぞれ特長が異なります。
「どこか1カ所にバックアップを取ったから安心」と考えるのではなく、それぞれの特長を踏まえて、複数のバックアップ先を使い分けるのがおすすめです。
4 バックアップの取り方

データのバックアップは、具体的にどのような手順で行えば良いのでしょうか。
スマートフォンとパソコンの各OSで、バックアップを取る方法をご紹介します。
4-1 スマートフォン
スマートフォンの場合、Androidなら「Googleドライブ」、iPhoneなら「iCloud」への自動データバックアップが行えます。
全てのデータがバックアップされるわけではありませんが、設定しておくと便利です。
【Androidの設定方法】
1.「設定」アプリを起動し、「システム」→「バックアップ」の順にタップする
2.「バックアップ」をオンにする
※Androidは機種やOSバージョンによって、手順や画面表示が若干異なる場合もあります。
この設定をしておくと、Googleアカウントにひも付けられているデータをバックアップすることができます。
【iPhoneの設定方法】
1.「設定」を開き、「ユーザー名」→「iCloud」の順に進む
2.バックアップを取りたい項目をオンにして、「iCloudバックアップ」をオンにする
パソコンを持っている場合は、スマートフォンとパソコンをUSBケーブルで接続して、内部のデータをパソコンにコピーしておく方法もおすすめです。
上記の方法でバックアップができないデータは、バックアップアプリなどを使用してバックアップしておくと良いでしょう。
4-2 Windows
写真や文書などの一部データは、パソコン内部から外付けHDDやオンラインストレージにコピー&ペーストで簡単にバックアップできます。
外付けストレージに自動でバックアップを取りたい場合は、以下の方法で設定を行ってください。
【Windows 10の場合】
1.パソコンにバックアップ用の外付けストレージを接続してから、画面下の検索窓に「更新」と入力
2.「更新プログラムの確認」→「ファイルのバックアップ」→「ドライブの追加」の順にクリックする
3.バックアップ先のメディアを選択すると、画面右側に「ファイルのバックアップを自動的に実行」と表示されるのでオンにする
4.必要に応じて、「その他のオプション」でバックアップの間隔やフォルダーを指定する
【Windows 11の場合】
1.バックアップ用の外付けHDDなどを接続して、画面左下の検索窓に「ファイル履歴」と入力する
2.「ファイル履歴」→「ドライブの選択」の順にクリックする
3.バックアップ先となる外付けストレージを選択して「OK」ボタンをクリックする
4.「詳細設定」からバックアップの頻度を設定して「変更の保存」をクリックする
5.「ファイル履歴」の画面に戻り「オンにする」をクリックしたら完了
4-3 Mac
macOS 10.5以降のMacは、「Time Machine」という機能を使って、内部データを丸ごと自動でバックアップすることができます。
【Time Machine機能の使い方】
1.外付けストレージを接続する
2.Appleメニュー→「システム環境設定」の順に選択し「Time Machine」をクリックする
3.「バックアップディスクを選択」をクリックして外付けストレージを選択し、「ディスクを使用」をクリックする
5 バックアップの取り方のルール

バックアップは、ルールに沿って取った方がデータを守りやすくなります。
データのバックアップを取る時は、以下の2点を意識することが大切です。
5-1 「3-2-1ルール」が基本
大切なデータは、できるだけ複数のストレージにバックアップを残しておきましょう。バックアップを1カ所にしか取っていないと、物理的なストレージの故障やシステム障害など、何らかの理由でデータが消えてしまう恐れがあります。
データのバックアップを取る時の考え方の基本に「3-2-1ルール」があります。これは、同じデータを3カ所に保管して、2つの異なる媒体を保存先としたうえで、1つは遠隔地に保存するという考え方です。
3-2-1ルールを厳格に守るのは難しいかもしれませんが、可能な限り複数のストレージにバックアップを取っておくことをおすすめします。
5-2 定期的にバックアップを取る
一回バックアップを取ったとしても、デバイスを使い続ける限りは取り扱うデータ量が増えていきます。大切なデータを失わないためには、定期的にバックアップを取ることが大切です。
失いたくない重要なデータはこまめにバックアップする、デバイス内の全データを定期的にバックアップするなど、バックアップに関するルールを決めておくと、大切なデータを失うリスクを抑えられます。
6 バックアップを取って重要なデータを守ろう

パソコンやスマートフォンなどに保存したデータは、デバイスの故障や操作ミスなどの理由で消えてしまう可能性があります。データの消失を完全に回避することはできないため、データの消失に備えた、定期的なバックアップの実施が重要です。
ただし、バックアップデータを保存したストレージなどが故障する恐れもあります。複数の場所にバックアップを取っておく、写真撮影時は複数のデバイスで撮るなど、同じデータを複数の異なる場所へ記録しておくことがおすすめです。