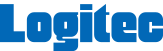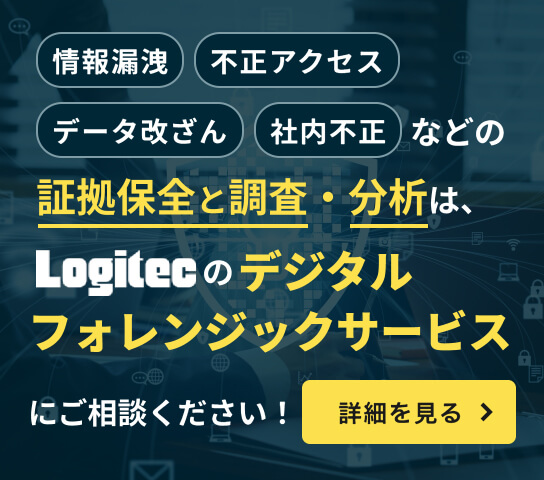近年、さまざまな場所で「ハラスメント」が話題に挙がることが増えてきました。いつでも誰でも、ハラスメントの被害を受けたり、無意識にハラスメントを行ったりしてしまうことも考えられます。
では、企業内部でパワハラやセクハラといったハラスメントが起きた可能性がある場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか。
ここでは、ハラスメントが疑われる際の、企業の内部調査の流れなどをご紹介します。
1 ハラスメントが疑われる場合は内部調査が必須!
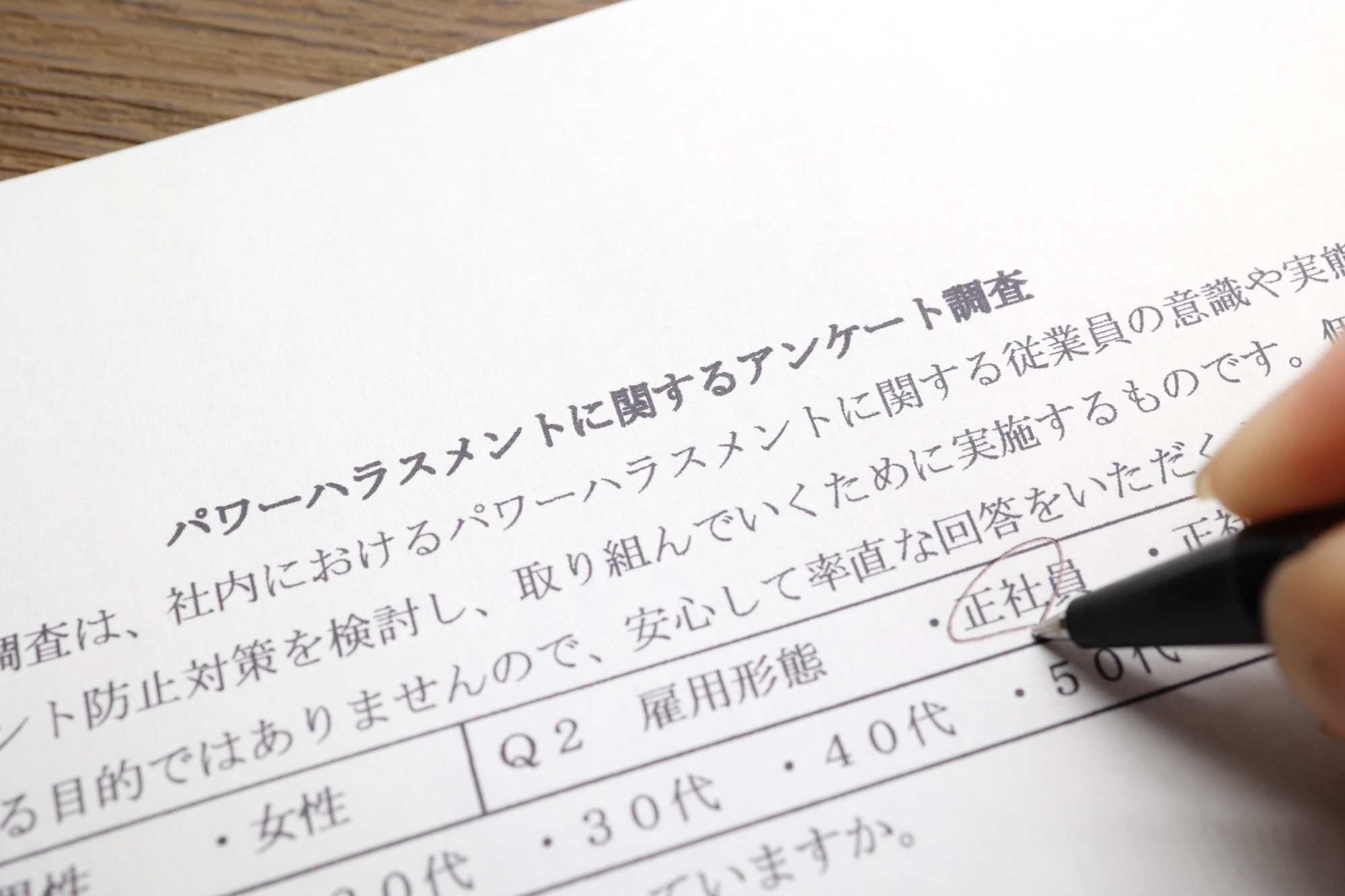
企業(事業主)には、パワハラやセクハラといったハラスメントを防止するために措置を講じることが義務付けられています。
従業員からハラスメントに関する相談を受けているにもかかわらず、それを放置することは許されません。
社内でのハラスメントが疑われる時は、事実確認や再発防止策を講じるために、内部調査を行う必要があります。
同僚や直属の上司では中立性が確保されにくいため、通常は複数人からなる調査委員会を設置して、内部調査を行うのが基本です。
また、社内の従業員だけで構成される調査委員会では社会的信頼性が低くなる恐れがあります。
事案の規模などにもよりますが、弁護士や社労士といった外部の人員も含めて調査を行うことを推奨します。
2 ハラスメントが疑われる時の調査の流れ
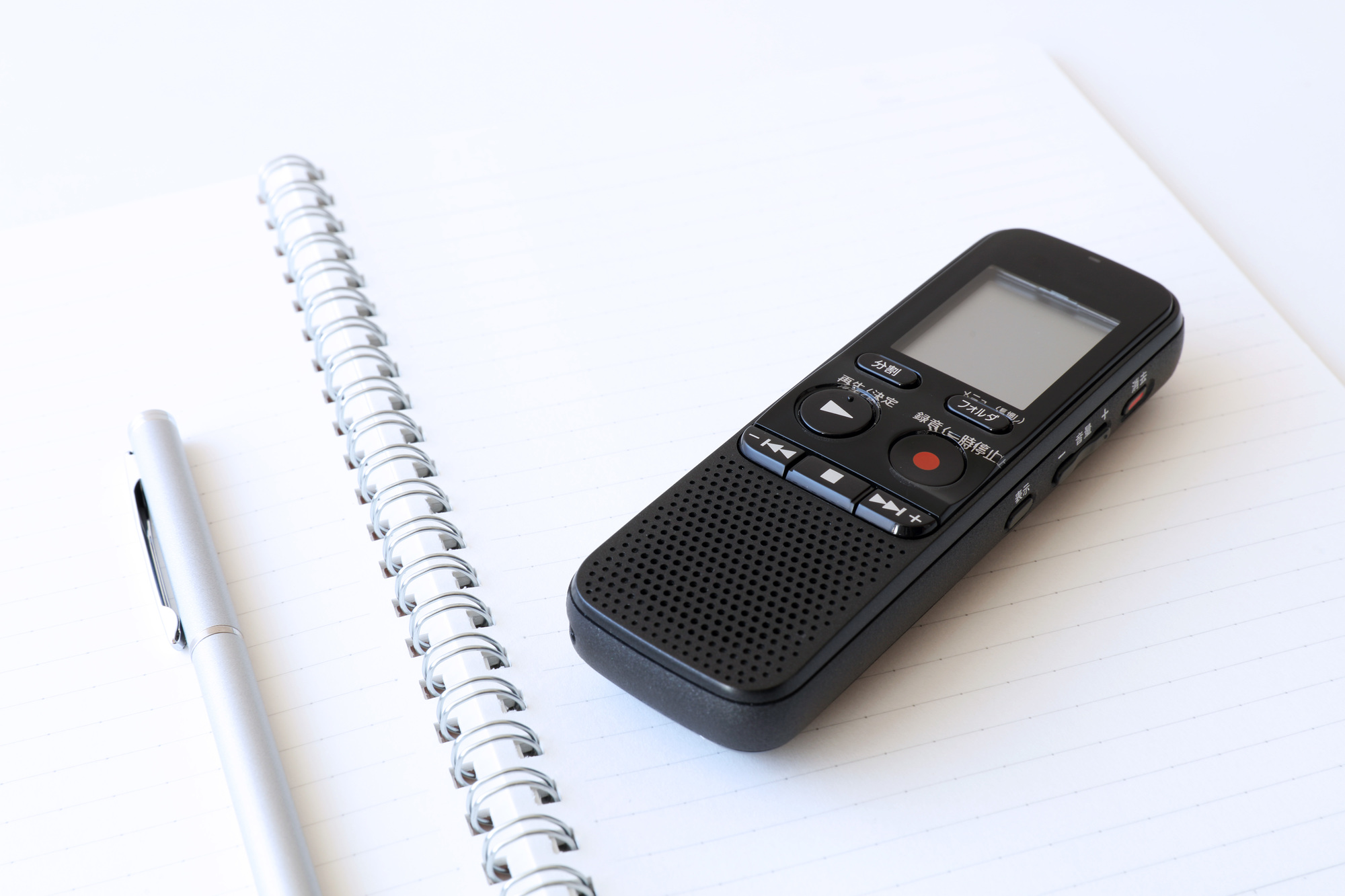
社内で何らかのハラスメントが疑われる時は、具体的にどのような調査を行えば良いのでしょうか。
内部調査の基本的な流れやコツは、以下のとおりです。
2-1 被害者からのヒアリング
被害者からハラスメントの相談を受けた時、最初に行うのは被害者の意向を聞くことです。何らかの理由で被害者が拒否した際は調査を控え、ハラスメントに関する注意喚起や研修の実施を行う程度にとどめます。
調査を希望する場合は、被害者と加害者を物理的に引き離したうえで、当事者からヒアリングを行います。
「言った、言わない」につながる恐れがあるため、それぞれの主張を録音したり、議事録を残したりしておきましょう。
ヒアリングでは、ハラスメントの内容や日時・場所、事案が発生するまでの経緯などを確認します。
ただし、被害者は不安を感じたり、戸惑ったりしている可能性が高いです。スムーズに内部調査を進めるために、被害者に不利益が生じないことなどを説明して、安心させることも心がけてください。
2-2 事実関係の確認
被害者から許可が下りた場合は、加害者にもヒアリングを行いハラスメントの詳細を調べます。
ただし、加害者側が自身の言動をハラスメントだと自覚していないことも考えられます。高圧的な態度や、被害者をかばうような態度を取るのではなく、中立的な立場から事実確認を行いましょう。
それぞれの主張が食い違っている場合は、被害者と加害者の同意を得たうえで、第三者にも事実確認をする必要があります。
2-3 適切な措置の検討
事実関係の確認が終わったら、ヒアリングや調査によって確認できた証拠に基づき、ハラスメントが本当に起きたのかどうかを判断します。
加害者の言動がハラスメントに該当する場合は、お互いを引き離す、加害者に懲戒処分を行うなどの措置が必要です。
ハラスメントに該当しないと判断された場合は、被害者に対して十分に説明を行いましょう。配置転換を行い、就業場所を変えるなどの対処が必要になることも考えられます。
3 内部調査のポイント
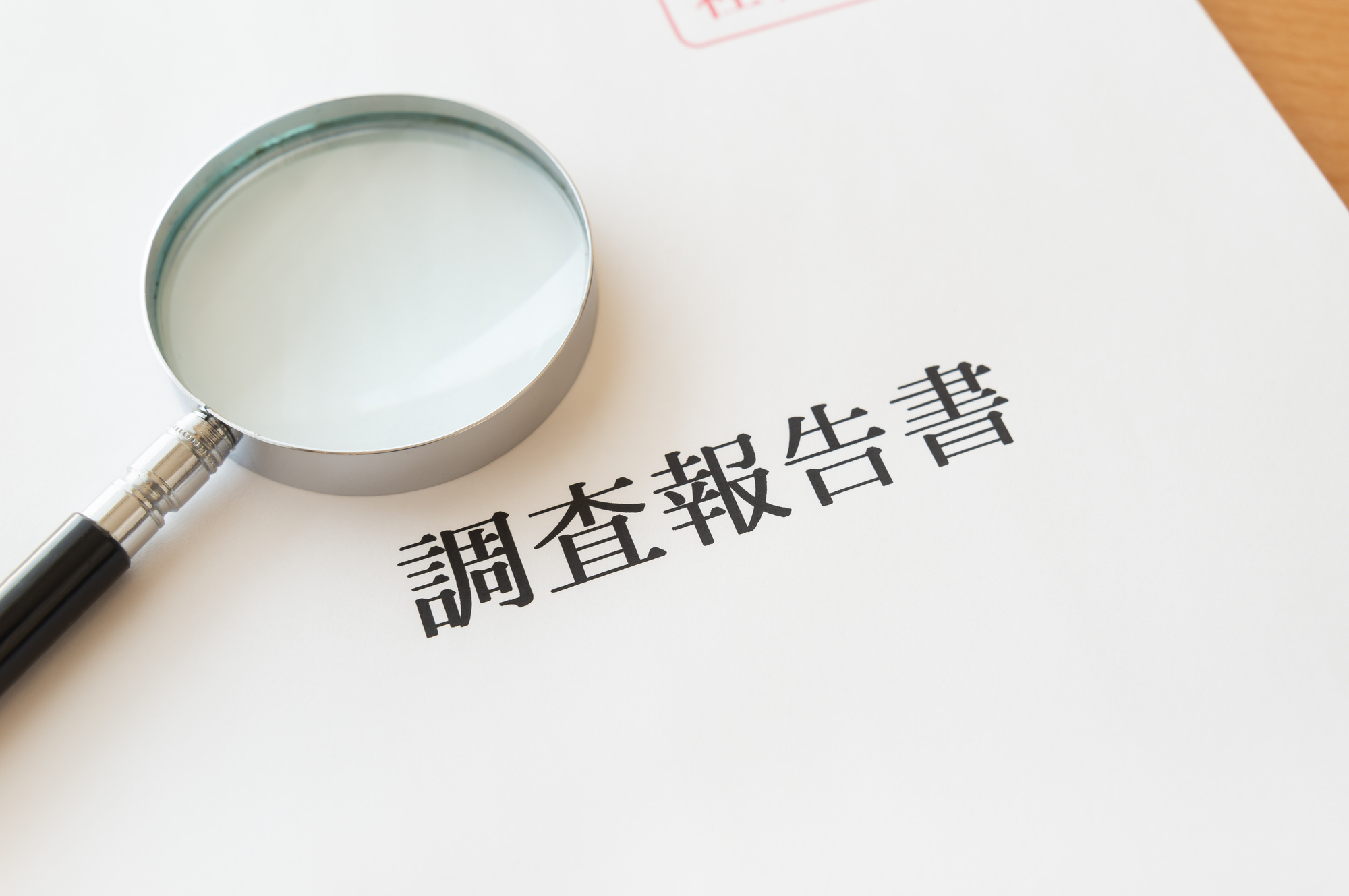
内部調査の行い方によっては、事実を見誤ったり、被害者・加害者を不快な気持ちにさせたりすることも考えられます。
実際に調査を行う際は、以下の点に注意が必要です。
3-1 中立の立場で調査する
内部調査の担当者は中立な立場に立ち、被害者・加害者どちらかの立場に寄らないように調査を進めることが大切です。
いずれかの立場に立ってしまうと、事実関係を見誤ってしまう恐れがあります。
被害者と仲が良い同僚や、加害者と関係性が深い部下など、中立な調査が難しい立場の人を担当者にするのは避けた方が良いでしょう。
3-2 プライバシーに配慮する
ハラスメントの内容などにも左右されますが、調査中は当事者のプライバシーに関する情報を取り扱う可能性が高くなります。
第三者から見えない場所でヒアリングを行うなど、被害者・加害者双方のプライバシーに配慮して調査することも求められます。
また、当事者以外に情報が広がらないよう、調査担当者は守秘義務を厳守することも重要です。
3-3 客観的な証拠を集める
フ当事者や第三者の発言が、絶対に正しいとは限りません。記憶違いや勘違いはもちろん、故意に発言が歪曲されている可能性も考えられます。
言い分が事実かどうかを判断するためには、客観的な証拠の確保も不可欠です。
客観的な証拠の例としては、当事者間のメールのやり取りや監視カメラの録画データ、写真、SNSサイトへの投稿などが挙げられます。
当事者へのヒアリングに加えて、確実にハラスメントがあったと判断できる証拠を集めることがポイントです。
4 証拠を確保するにはデータ保全が重要

前述のとおり、メールやSNSへの投稿、録画データといったデジタルデータも、ハラスメントの判断材料になり得る重要な証拠です。
しかし、デジタルデータは簡単に削除できてしまうものです。対応が遅れると、加害者に証拠となるデータを消されたり、第三者が誤操作でデータを上書きしたりすることも考えられます。
ハラスメントが疑われる時は、証拠を確実に残すためにデータを保全することが大切です。
ロジテックのデジタルフォレンジックサービスは、データを書き換えることなく保全することができます。ハラスメントが疑われる際の調査でお困りの時は、お気軽にご相談ください。
5 ハラスメントに対しては迅速な対応が必須!

社内でハラスメントの発生が疑われる場合、企業は事実関係の調査を実施しなければいけません。
当事者のメールなど、証拠となるデータを消されてしまう恐れがある点にも注意が必要です。ハラスメントが疑われたら、迅速に対応することを心がけましょう。